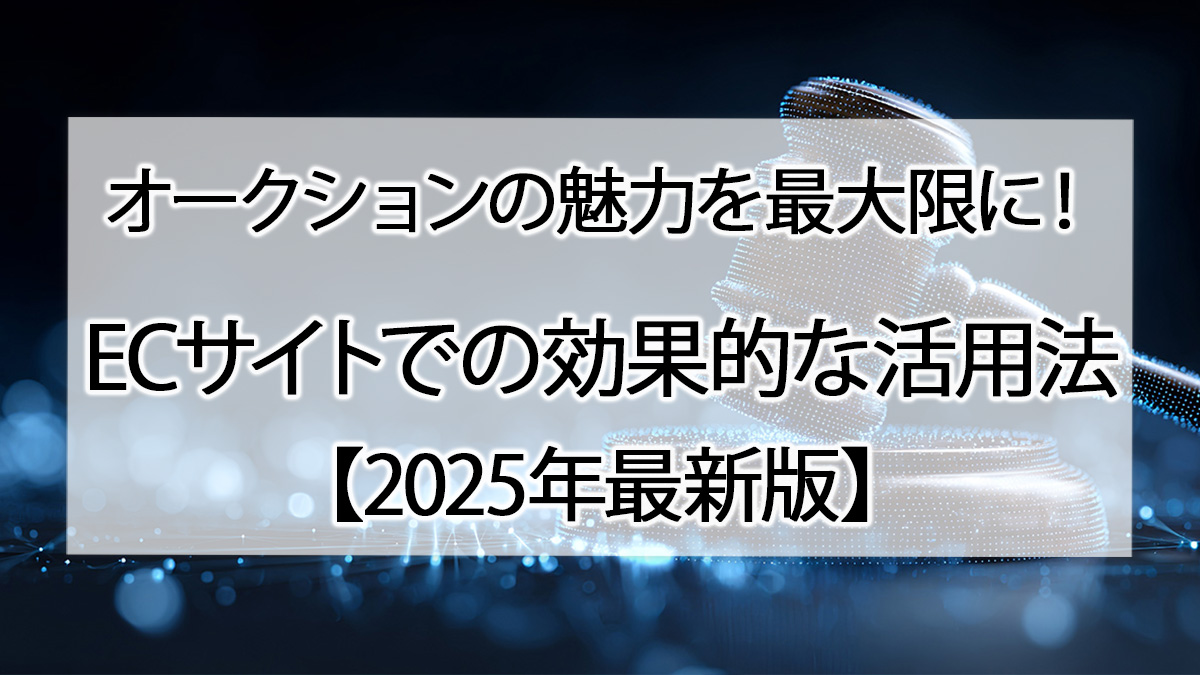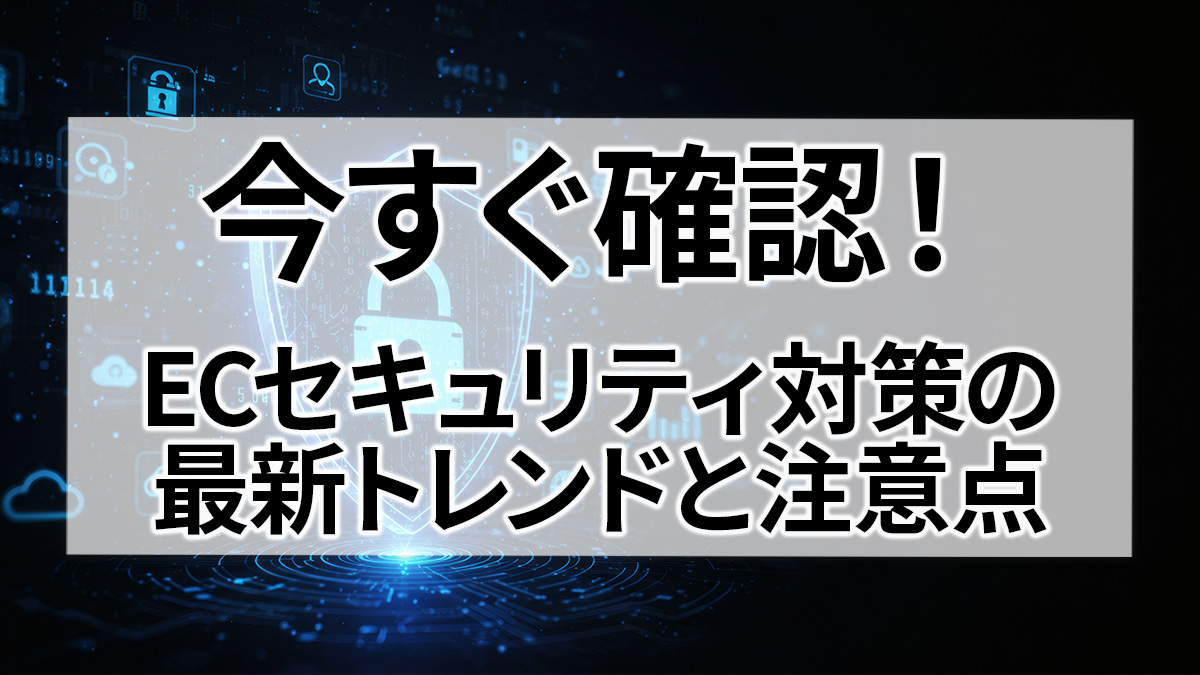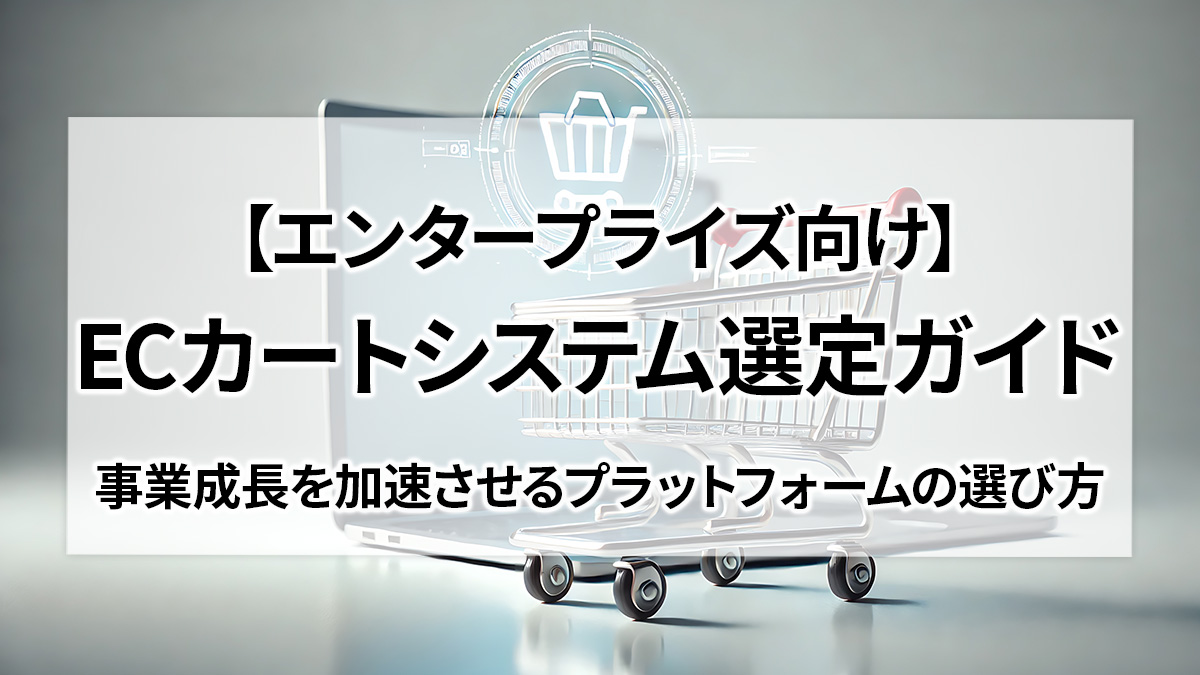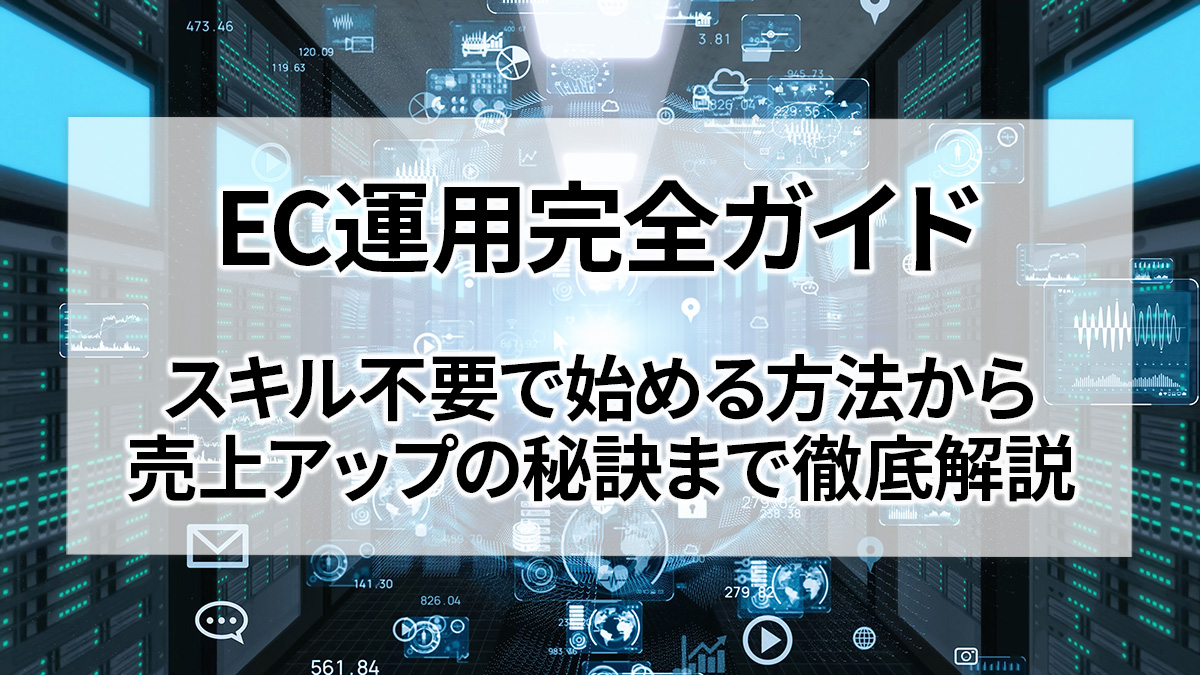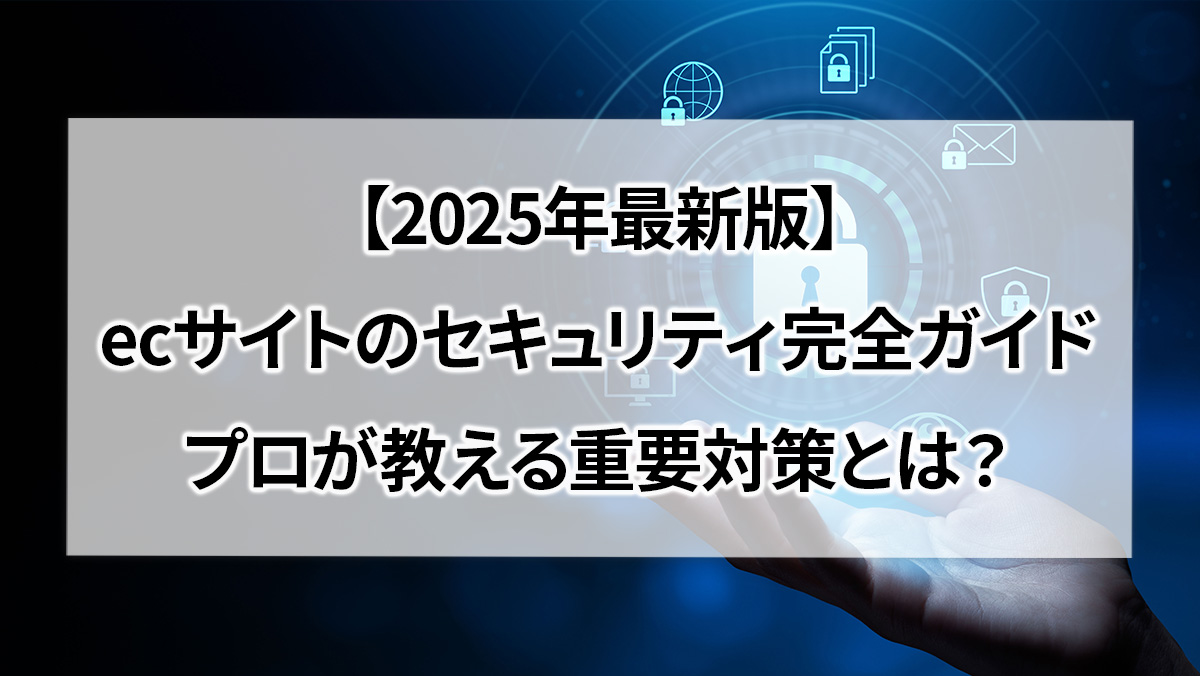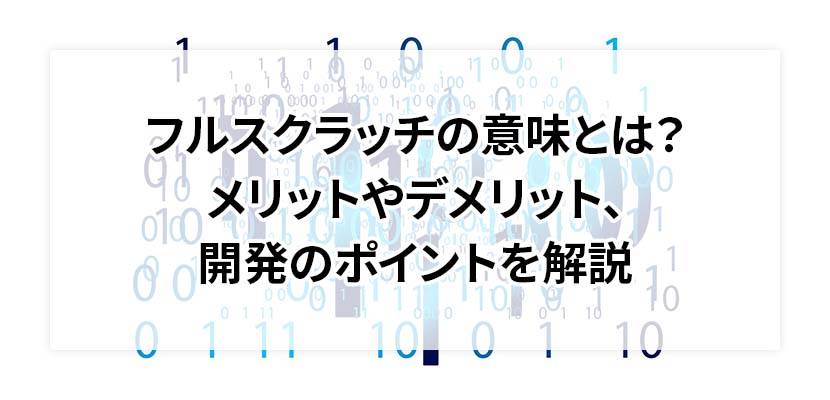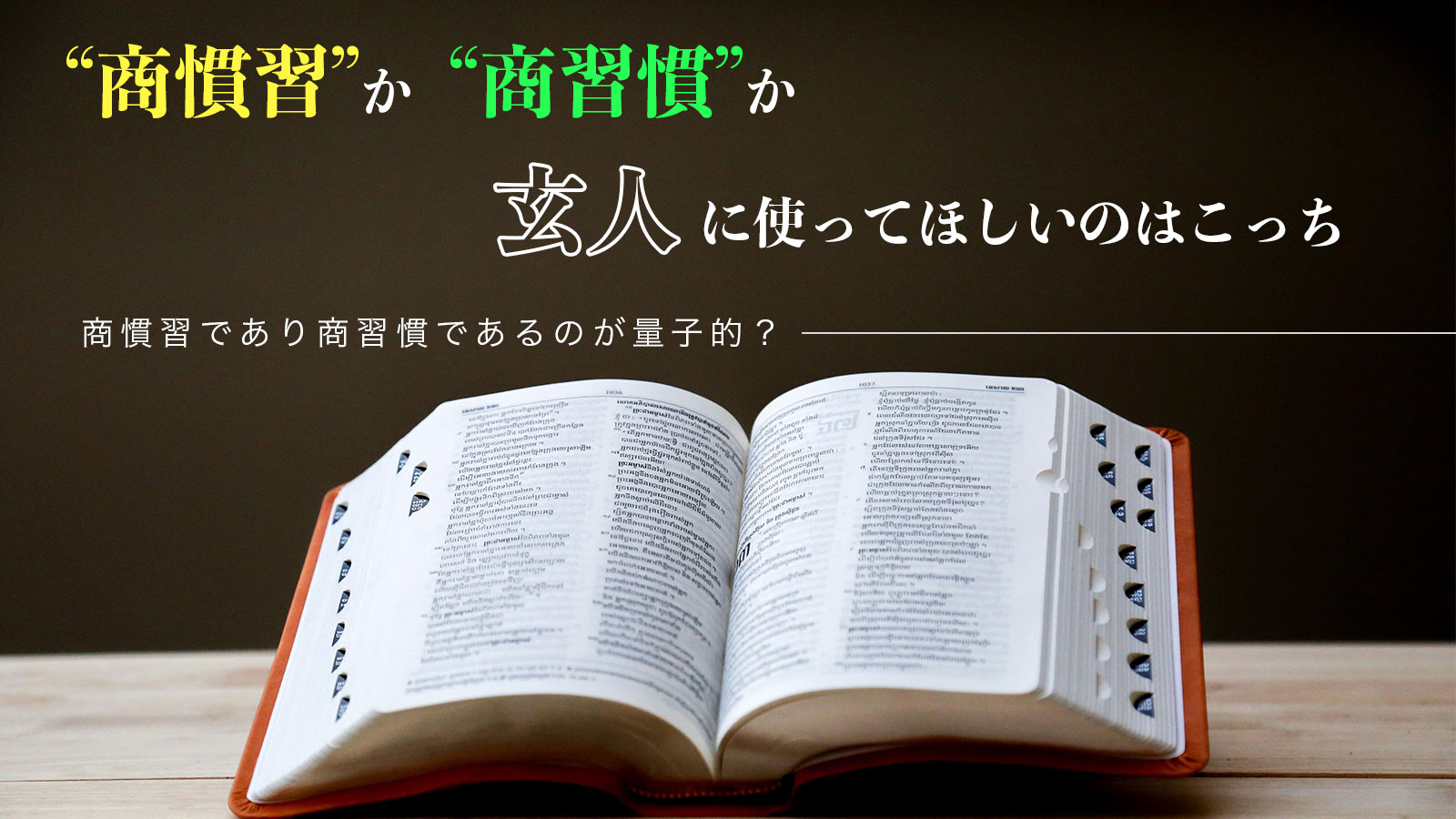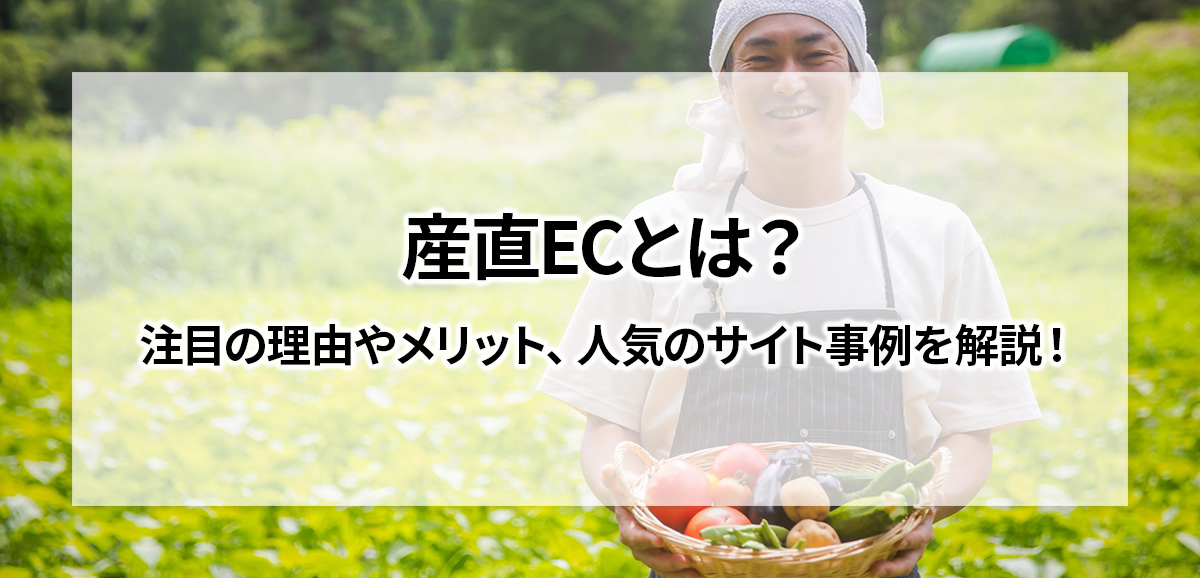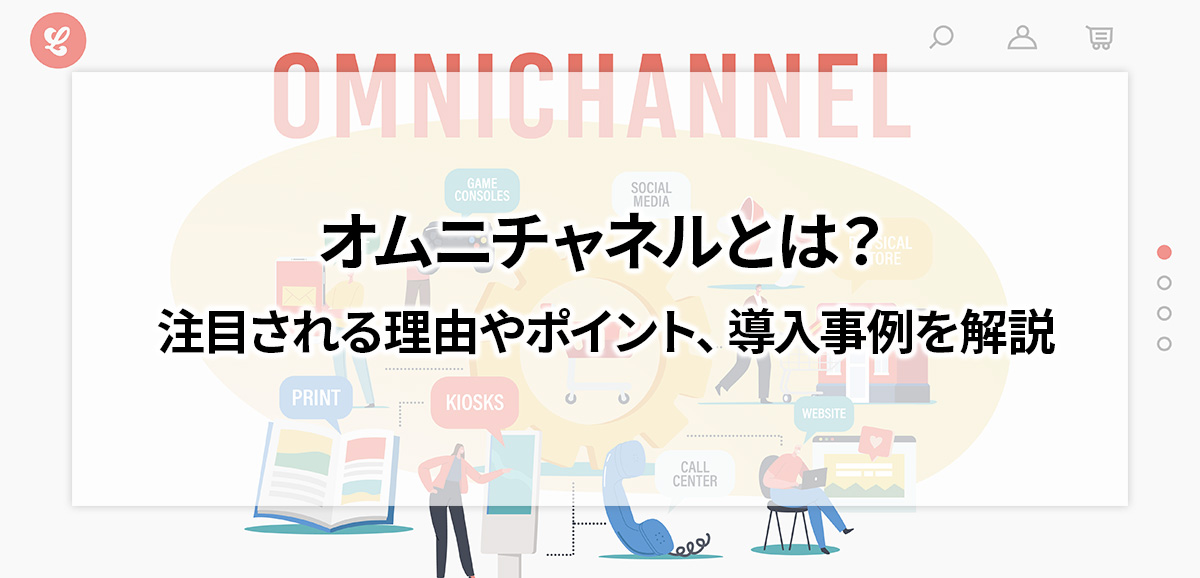- 最終更新日: 2025.06.18
- 公開日:2022.02.07
【2025年最新】OMOとは? “最高の顧客体験”を実現する新常識を、初心者にも分かりやすく解説
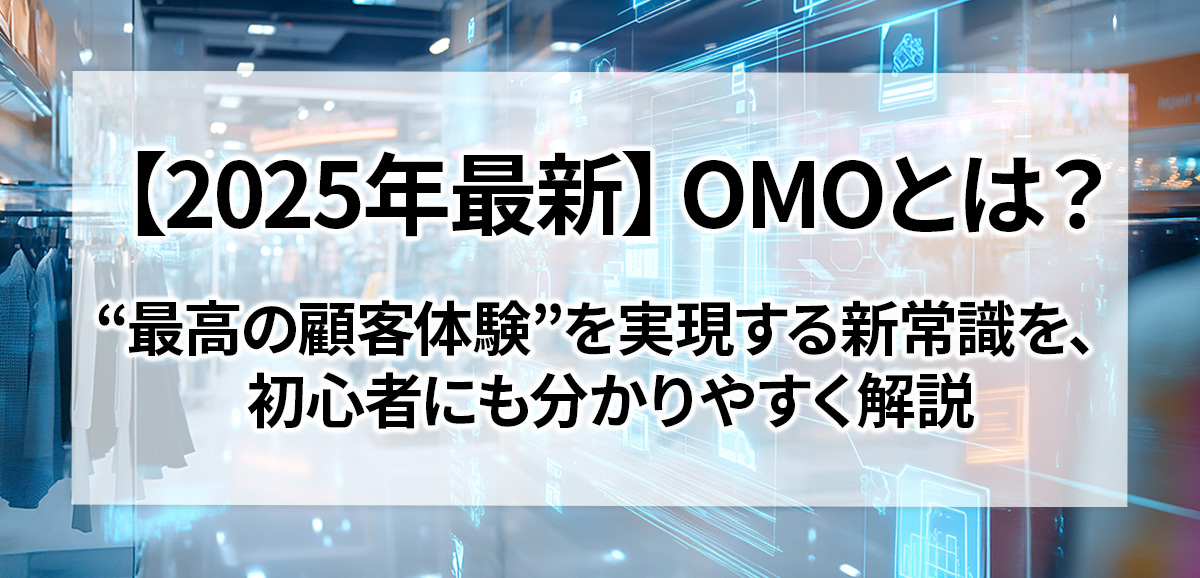
- BtoC
- EC
- オムニチャネル
- お役立ち情報
- マルチサイト
- 事例
- 用語・知識
お店で商品を下見して、買うのは自宅のソファからネットで。SNSの投稿で見かけて欲しくなり、週末に実店舗へ足を運ぶ。
私たちにとって、オンライン(ネット)とオフライン(実店舗)の世界を自由に行き来する買い物は、もはや当たり前の光景となりました。
このような消費行動の変化に応え、顧客とより深く、長く良好な関係を築くための鍵となるのが「OMO(オーエムオー)」という考え方です。
この記事では、2025年のビジネスシーンにおける最新トレンド「OMO」の本質を、その背景から具体的な企業の取り組みまで、誰にでも分かるように、かみ砕いて解説します。
目次
OMOとは? ― オンラインとオフラインの「壁」が消える世界
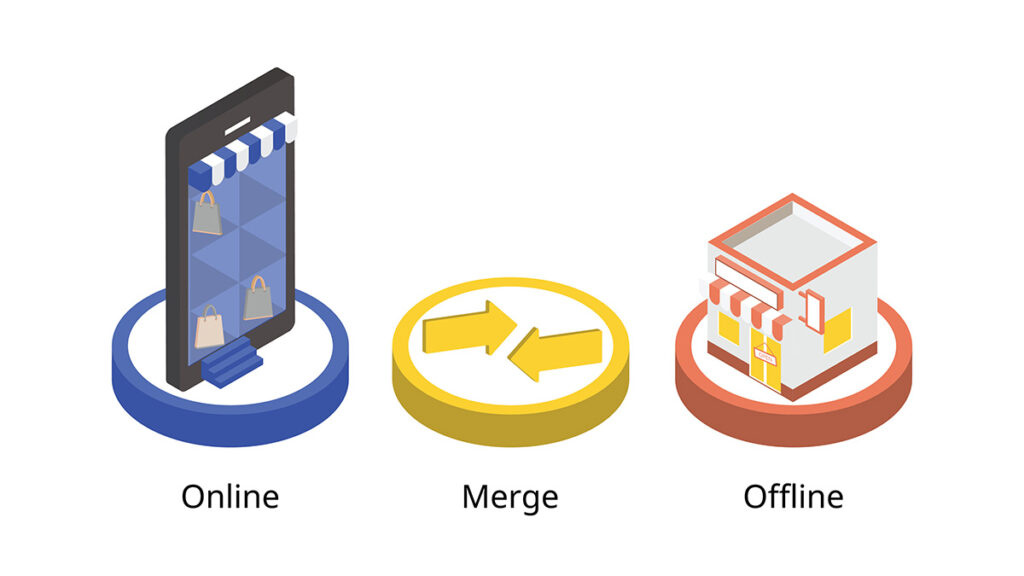 OMOとは「Online Merges with Offline」の略で、直訳は「オンラインとオフラインの融合」です。
OMOとは「Online Merges with Offline」の略で、直訳は「オンラインとオフラインの融合」です。
その本質は、よりシンプルです。顧客の視点に立てば、ネットの世界もお店も、区別のない「一つの便利で楽しい買い物体験」として提供すること。これこそがOMOの目指す世界です。
よく似た言葉「O2O」「オムニチャネル」との違い
OMOをより深く知るために、よく似たマーケティング用語との違いを見てみましょう。進化の順番で考えると、非常に分かりやすくなります。
| 用語 | イメージ | 目的 |
|---|---|---|
| O2O | 矢印 | ネットからお店へ、お店からネットへ「人を動かす」こと |
| オムニチャネル | 壁の撤去 | どのチャネル(お店、EC、アプリ)でも「同じように買い物ができる」こと |
| OMO | 世界の融合 | 顧客一人ひとりにとって「最高の体験をデザインする」こと |
- ステップ1:O2O(Online to Offline)
「アプリでクーポンを配信して、お店に来てもらう」のが典型例です。オンラインとオフラインは別々の場所として存在し、その間を顧客が移動するイメージです。 - ステップ2:オムニチャネル
「ECサイトで注文した商品を、店舗で受け取る」「お店で貯めたポイントが、ECサイトでも使える」など、チャネル間の壁を取り払い、顧客の利便性を高める考え方です。 - ステップ3:OMO
オムニチャネルがさらに進化した世界です。そもそもオンラインとオフラインを区別せず、すべてのデータを連携させます。「ECサイトであなたがよく見ている商品を、お店のスタッフが把握していて、さりげなく提案してくれる」といった、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな体験の提供を目指します。
OMOがもたらす3つの大きな価値
 OMOを導入すると、企業と顧客の双方にどのような良いことがあるのでしょうか。
OMOを導入すると、企業と顧客の双方にどのような良いことがあるのでしょうか。
顧客を「点」ではなく「線」で理解できる
これまではバラバラだったECサイトでの閲覧履歴や店舗での購買履歴といったデータが、OMOによって一人の顧客を軸とした「線」で繋がります。これにより顧客の好みや行動パターンを深く理解でき、本当に求められている商品やサービスの開発に繋がります。
顧客の「買いたい気持ち」を逃さない
「お店に欲しいサイズがない…」そんな時でも、スタッフがその場でタブレットを使い、ECサイトの在庫を確認して自宅へ配送手続きをしてくれる。このように、あらゆる場面で顧客の「買いたい」という気持ちを逃さず、スムーズな購買体験を提供することで、機会損失を防ぎます。
ただの顧客から「大好きなファン」へ
一貫性のある快適な体験は、顧客満足度を大きく向上させます。満足が信頼へ、そしてブランドへの愛着(ロイヤルティ)へと育っていくことで、顧客は一度きりのお客様ではなく、長く付き合える「ファン」になってくれるのです。これは、企業の長期的な成長にとって最も重要な資産となります。
OMO実現を阻む「3つの壁」と乗り越え方
 OMOは非常に強力ですが、その実現は簡単ではありません。多くの企業が直面する「3つの壁」と、その乗り越え方を知っておきましょう。
OMOは非常に強力ですが、その実現は簡単ではありません。多くの企業が直面する「3つの壁」と、その乗り越え方を知っておきましょう。
コストの壁(時間と費用)
顧客データを一つにまとめるシステム(CDPなど)の導入や、各部門が使うツールの連携には、相応の投資と時間が必要です。一気に完璧を目指すのではなく、まずは特定の領域から小さく始めて効果を検証する「スモールスタート」が、乗り越えるための現実的なアプローチです。
組織の壁(部門間の対立)
「EC部門の売上」と「店舗部門の売上」を別々に評価していると、「なぜ自分たちの売上を犠牲にしてまで協力しなければならないのか」という対立が生まれます。これを乗り越えるには、経営層がリーダーシップを発揮し、「顧客体験の向上」という全社共通のゴールを設定することが不可欠です。
データの壁(集めるだけで活用できない)
高価なシステムを導入してデータを集めても、それを分析し、改善アクションに繋げる人材やノウハウがなければ宝の持ち腐れです。「このデータをどう活用し、お客様を喜ばせるか」という具体的なシナリオを事前に設計し、分析できるチームを確保・育成することが重要になります。
【2025年最新】OMOが生み出す新しい買い物体験(トレンド&事例)
 それでは、OMOは具体的にどのような新しい体験を生み出しているのでしょうか。最新のトレンドと、それを体現する企業の事例をセットでご紹介します。
それでは、OMOは具体的にどのような新しい体験を生み出しているのでしょうか。最新のトレンドと、それを体現する企業の事例をセットでご紹介します。
トレンド1:AIが「私の専属コンシェルジュ」になる
AI、特に生成AIの進化により、オンライン・オフラインの膨大なデータを活用したパーソナライゼーションは新たな次元に入りました。一人ひとりに最適化された提案が、より自然な形で行われます。
- 【事例】NIKE(ナイキ)
公式アプリは、まさにOMO戦略の心臓部です。アプリでの閲覧・購買履歴から、あなたの好みをAIが学習。限定商品の情報が届くだけでなく、店舗に行けば、アプリ会員限定のスムーズな決済や、あなたに合った商品提案を受けられます。オンラインのデータが、オフラインでの特別な体験を生み出しているのです。
トレンド2:「売る場所」から「体験する場所」へ変わる店舗
店舗の役割は、商品を売るだけでなく、ブランドの世界観に触れたり、商品を試したりする「体験の場」へとシフトしています。
- 【事例】UNITED ARROWS(ユナイテッドアローズ)
同社の公式アプリでは、気になる商品の店舗在庫をリアルタイムで確認し、取り置きまで依頼できます。オンラインで下調べをして、オフラインの店舗で安心して試着・購入するという、スムーズな連携を実現。また、カリスマ店員のスタイリング投稿を参考にできるなど、オンラインでも店舗のような繋がりを感じられる工夫が満載です。
トレンド3:オフライン体験の課題を「テクノロジー」で解決する
これまで当たり前だったオフラインでの「不便」を、テクノロジーで解消する動きが加速しています。
- 【事例】Amazon(テクノロジーの試行錯誤)
Amazonは、かつて注目された無人決済店舗「Amazon Go」で培った「Just Walk Out」技術を、空港やスタジアムなど小規模な店舗フォーマットや第三者へ提供しています。一方で、自社のスーパーマーケット「Amazon Fresh」では同技術からスマートカート(Dash Carts)へ移行するなど、常に最適な顧客体験を模索し、試行錯誤を続けています。オフライン体験の課題解決に対するこの飽くなき姿勢こそが、OMOを考える上で参考になります。
まとめ:OMOとは、顧客と深く心を通わせるための「考え方」
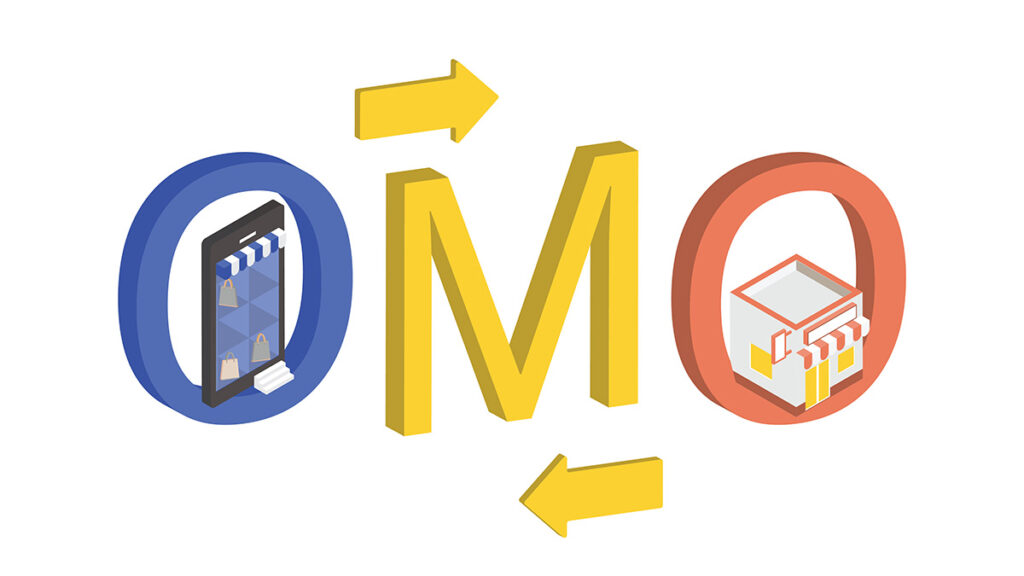 ここまで、OMOの本質から最新事例までを解説してきました。
ここまで、OMOの本質から最新事例までを解説してきました。
OMOは、難しい専門用語や複雑なITシステムの話だけではありません。その根底にあるのは、「どうすれば、お客様ともっと仲良くなれるだろう?」「どうすれば、もっとお買い物を楽しんでもらえるだろう?」という、非常にシンプルで温かい思想です。
テクノロジーの進化と共に、OMOの形はこれからも変わり続けるでしょう。しかし、顧客一人ひとりに真摯に向き合うというその本質は変わりません。
まずはあなたの会社のサービスを、一人の顧客として体験してみてください。そこに、OMO実現への第一歩となるヒントが隠されているはずです。